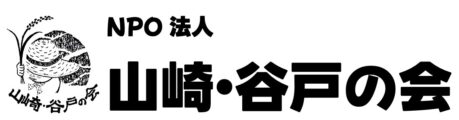谷戸の自然だより 今年の9月から10月の気象と自然の様子
記録的な残暑が続き、9月も真夏の延長でした。関東でも鎌倉だけは、40日以上雨が降らず田んぼがひび割れてしまいました。9月5日に突然、大雨が降り、谷戸の土手が崩れました。田んぼや湿地は、やっと水不足が解消しました。10月20日の時点では、まだ台風の直撃はありません。3年連続で直撃をを免れていることになります。
猛暑や水不足の影響か、秋の野草の花が咲くのが遅れ、秋の湿地をいろどるミゾソバの花が半月遅れでようやく咲き始めました。
●9月から10月の谷戸でよかったこと心配なこと
よかったこと
春から姿を見せなかったミツバチ(野生のニホンミツバチ)が、9月頃から時々見られるようになりました。ミツバチは暑いと産卵が少なくなるそうですが、気温が下がってきたからでしょうか。10月15日、ノビ
タキという野鳥が本田の近くで撮影されました。夏に高原で繁殖し、秋に南へ渡っていく途中、谷戸に立ち寄ったのです。鎌倉では珍しい記録です。草原の鳥なので、田んぼとオギ原があることが、ノビタキを引き寄せたのでしょう。谷戸に里山環境がある証拠です。
心配なこと
今年の秋もアキアカネが少ないようです。湿地の花に来るトラマルハナバチなど昆虫の姿も少なめです。猛暑は昆虫に大きく影響しているようです。
●田んぼの水不足 40年前と今
谷戸の田んぼの水は、①上流の湿地から水路で流れて来る水、②畔から染み出してくる水(絞り水)、③斜面の林から入ってくる水の3種類があります。現在は、③の水は目で確認できませんが、40年前は、山側の土手から竹筒で、水を田んぼ(細田といわれる区画)に落とし込んでいました。山の斜面からいつも水が出ていたのです。②は③とも関係していますが、田んぼに入ると冷たい箇所があるのでわかります。この水は、夏は冷たく冬は暖かいので、ヘイケボタルの幼虫が育っていると思われます。30年くらい前まで、田んぼのヘイケボタルは今よりたくさんいて100匹くらいは見られました。畔から染み出してくる絞り水が豊富だったのでしょう。今年の雨不足で、①が明らかに減少しました。上流の湿地も水不足だったので、どうにもなりませんでした。さらに田んぼの水不足の原因として、湿地から田んぼへ流れる地下水脈の分断が考えられます。谷戸が公園化されるとき、田んぼの上流に横断道が作られたからです。横断道の下に水路を作って、田んぼに流れ込むようになっていますが、地下水脈への影響は不明です。おそらく水が滞っているのでしょう。そのため、上流の湿地にガマが多く生えているのかもしれません。根本的な対策は難しいですが、湿地の保全とも合わせて、谷戸全体の乾燥化対策を考えていきたいと思います。